「全く戦わずに勝つことは不可能でしょう。ただ、戦い、つまり損失を最小限に押さえて勝つことは可能ですぞ」
「その方法とは?」
「自分を磨きなされ。国を磨きなされ。そして、最強になりなされ。そうすれば、敵も戦いを避け、自分から進んで味方になりにきましょうぞ。敵もバカではありませぬ。初めから負けると分かっている戦争など、決して行いませぬ」
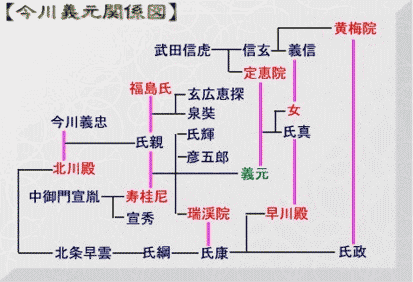
「なるほど」
義元は納得した。
| 1.花倉の乱 | ||||||||||||||
ホーム>バックナンバー2002>1.花倉(はなくら・はなぐら)の乱
|
今川氏は名門である(「今川氏系図」参照)。
足利氏の支流だから、八幡太郎(はちまんたろう)源義家の子孫である。鎌倉時代の武将・足利国氏(くにうじ)が、父から三河今川荘(愛知県西尾市)を与えられ、初めて今川姓を称した。
南北朝時代の当主・今川範国(のりくに)は、源氏の棟梁(とうりょう)・足利尊氏に従って各地を転戦し、駿河・遠江二か国の守護に任ぜられた。
以後、下克上の嵐にも吹き飛ばされることなく、今川氏の当主は代々この土地を守り続けた。一時期、遠江を奪われたが、今川氏親(うじちか)の代に奪還に成功している。
| 今川義元 PROFILE | |
| 【生没年】 | 1519-1560 |
| 【別 名】 | 方菊丸・梅岳承芳 |
| 【出 身】 | 駿河国府中(静岡市) |
| 【本 拠】 | 駿府館(静岡市) |
| 【職 業】 | 戦国大名(駿河・遠江・三河国主) |
| 【役 職】 | 駿河守護(1536-1560) ・遠江守護(1536-1560)・三河守護 ・治部大輔・上総介・三河守 |
| 【位 階】 | 従四位下 |
| 【 父 】 | 今川氏親 |
| 【 母 】 | 寿桂尼(中御門宣胤女) |
| 【兄 弟】 | 今川氏輝・彦五郎?・玄広恵探 ・泉奘?・氏豊・瑞渓院(北条氏康室) ・女(中御門大納言室)・女(牟礼郷右衛門室) ・女(瀬名氏俊室)・女(関口氏広室) |
| 【 妻 】 | 定恵院(武田信虎女) |
| 【 子 】 | 今川氏真・長得ら |
| 【 師 】 | 太原崇孚(雪斎) |
| 【盟 友】 | 武田信虎・武田信玄・北条氏康 |
| 【部 下】 | 鵜殿長照・朝比奈泰能・瀬名氏俊 ・関口氏広・岡部元信・松平元康ら |
| 【仇 敵】 | 福島正成・北条氏綱・織田信秀 ・織田信長ら |
| 【墓 地】 | 高徳院(愛知県豊明市) ・古戦場公園(名古屋市緑区) ・臨済寺(静岡市) ・大聖寺(愛知県豊川市) ・今川塚(愛知県東海市) |
今川義元は永正十六(1519)年に駿府(すんぷ。駿河府中。静岡県静岡市)で生まれた。
父は氏親で、母は権大納言・従一位まで昇った公家・中御門宣胤(なかみかどのぶたね)の娘、寿桂尼(じゅけいに)である。幼名は方菊丸(ほうぎくまる)。
正室の子であったが、五男(または三男とも四男とも)だったため家督継承権はなく、幼くして寺に入れられた。善徳寺(善得寺。静岡県富士市)という寺である。法名は梅岳承芳(栴岳承芳。ばいがくしょうほう)というが、以後は義元で統一する。
大永六年(1526)、父・氏親は五十四歳で没し、長兄・今川氏輝(うじてる)が家督を継いだ。まだ十四歳の少年であった。当然、次の家督は氏輝の子、次の次はその子の子、ということになる。
「余はいてもいなくても、どうでもいい人間なんだ」
いじける義元に、住職が近寄ってきた。
太原崇孚(たいげんすうふ・そうふ)――。号は雪斎(せっさい)。今川家の重臣・庵原(いおはら・いはら)氏の出身で、臨済宗妙心寺派(みょうしんじは)大本山・妙心寺(京都市右京区)で修行した高僧である。
「将来のために学問に励むことですな。家臣がでしゃばる国には、間もなく争乱が起きましょう。必ずや今学んでいることが役に立つ時が来ましょうぞ」
当時、今川家の当主が少年であることをいいことに実権を握っていた一族があった。
先代氏親の側室の一族、福島(くしま)氏である。特に遠江高天神城(たかてんじんじょう。静岡県掛川市)主・福島正成の横暴には目に余るものがあった。義元のところにも、正成のうわさは入ってきていた。
太原崇孚は説いた。
「あなたが僧であることは、不幸ではなく、好機なのですぞ。あなたには時間がある。無限の可能性がある」
義元は学んだ。そして、今川家の栄光の歴史を知った。
「今川家は将軍家と同族だったのか。管領家にも劣らない名家だったのか。天下に号令してもおかしくない一族だったのか――」
義元は飲み込みが速かった。
そのため太原崇孚は、次から次へといろいろな書物を持ってきた。
『難太平記(なんたいへいき。今川了俊著)』・『今川状(いまがわじょう。道徳教科書。了俊著)』・『今川大双紙(いまがわおおぞうし。武家礼儀作法説明書)』など今川家に代々伝わる書物、『論語(ろんご)』・『孟子(もうし)』・『庭訓往来』といった教育書。『古事記』・六国史・四鏡・『平家物語』・『太平記』といった歴史物、『古今和歌集』・『新古今和歌集』といった歌集。『尊卑分脈(そんぴぶんみゃく)』といった系譜集などなど。
| 七書 |
| 孫子(そんし) 呉子(ごし) 司馬法 尉繚子(うつりょうし) 三略 六韜(りくとう) 李衛公問対 |
太原崇孚は特に軍学の教授に力を入れた。
中国には、七書(しちしょ。武経七書)と呼ばれる軍学書がある。
なかでも中国春秋時代の軍学者・孫武(そんぶ)が記したとされる『孫子』はその筆頭で、最も有名な軍学書であった。
『孫子』は信玄の愛読書として知られているが、希代の軍師である太原崇孚が義元にこれを勧めなかったはずはない。後々の義元の戦いぶりを見ても、とても読んでいなかったとは考えられないのである。
やはり義元も、『孫子』を愛読していたのであろう。いや、むしろ年下の信玄のほうが義元の影響を受けてこれを読み始めたのではなかろうか。
『孫子』には、戦争の極意について、次のように説く。
およそ用兵の法は、国を全(まっと)うするを上となし、国を破るはこれに次ぐ。
軍を全うするを上となし、軍を破るはこれに次ぐ。
旅(旅団)を全うするを上となし、旅を破るはこれに次ぐ。(以下中略)
この故に百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。
戦えば、兵力を消耗する。負ければなおさら勝っても多少は兵力を消耗する。戦わなければ、兵力を消耗することはない。味方も敵も全く損失を被ることはない。したがって戦いに勝つことより、戦わずに味方にしてしまうことが一番だと説いているのである。
考えてみれば、当たり前のことである。いつの時代でも通じることである。けれども、理屈では分かっていても、なかなか実行できることではない。しかも当時は戦国の世。敵と戦わずして勝つことなど、どう考えても無理なことのように思えた。
義元の疑問に、太原崇孚は答えた。
「全く戦わずに勝つことは不可能でしょう。ただ、戦い、つまり損失を最小限に押さえて勝つことは可能ですぞ」
「その方法とは?」
「自分を磨きなされ。国を磨きなされ。そして、最強になりなされ。そうすれば、敵も戦いを避け、自分から進んで味方になりにきましょうぞ。敵もバカではありませぬ。初めから負けると分かっている戦争など、決して行いませぬ」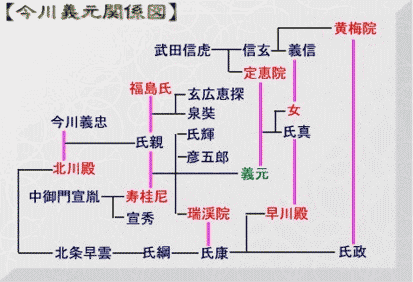
「なるほど」
義元は納得した。
なるべく敵と戦わずに勝つ!
以後、これが義元の信条となった。
天文五年(1536)、義元の長兄・氏輝が二十四歳で急死した。
同日、どういうわけか次兄・今川彦五郎も亡くなっている。福島氏に殺されたのであろうか?(氏輝の幼名は五郎というので、あるいは二人は同一人物だったのかも知れない)
実力者・福島正成は奮い立った。
「今こそ、我が一族の子を今川家の当主に立てるべし」
我が一族の子とは、三兄(または次兄)・今川良真(りょうしん・よしざね)である。側室福島氏から生まれ、当時は花倉(はなくら・はなぐら。静岡県藤枝市)の遍照光寺(へんじょうこうじ。遍照寺)の住職をしていた。法名は玄広恵探(げんこうえたん)。
「氏輝殿の弟の中では、玄広恵探殿が一番年上ですぞ」
朝比奈(あさひな)氏・篠原(しのはら)氏・斎藤(さいとう)氏といった有力豪族も、こぞって玄広恵探を推した。
だが、寿桂尼としては、継子よりも実子の義元に家を継いで欲しい。
「良真は側室の子。義元は正室の子じゃ」
寿桂尼はそう主張して譲らなかった。
太原崇孚も、
「義元殿のほうが見込みがある」
と、彼女に賛同、義元方には岡部(おかべ)氏・瀬名(せな)氏・孕石(はらみいし)氏といった有力豪族がなびいた。
今川家中は、義元派と玄広恵探派、真っ二つに分かれたのである。
寿桂尼は駿府館(静岡市)に福島正成らを招いて説得を試みたが、失敗に終わった。
正成ら玄広恵探派は、遍照光寺の近くにある花倉城(葉梨城)を拠点に兵を挙げ、方上城(かたがみじょう。静岡県焼津市)を占拠、駿府館を襲撃したため、寿桂尼は久能山(くのうざん。静岡市)へ逃れた。
「大変なことになった」
義元は知らない間に国を二分する戦いの当事者になっていた。
太原崇孚は喜んだ。
「義元殿、今まで学んだことが生かされるときが、とうとうやってきましたぞ」
「そんなふうに言われても、余は戦争ど素人だ。いったい何をしていいのか分からない」
困り果てる義元に、太原崇孚が助け舟を出した。
「あなたの信条はなんですか?」
「『なるべく敵と戦わずに勝つ!』だ」
「では、そのとおりになされよ」
「それだけでは分からない。もう一言、助言を」
「『敵の敵は味方』と、いいますな」
「敵の敵は味方――」
義元はひらめいた。
福島正成の最大の敵は、隣国甲斐の領主・武田信虎(たけだのぶとら。信玄の父)である。ついこの間まで今川・武田両氏は仲が悪く、正成は氏親・氏輝の命令で何度か甲斐に攻め込んでいた。信虎はそのたびに正成を撃退したが、武田方の損害も大きく、正成のことを目の敵にしていた。
「その信虎なら味方になってくれるだろう」
義元は甲斐に使者を送った。
「正成を討つだと。それは願ってもないこと」
義元の読みは当たった。信虎は喜んで援軍をよこしてきた。
「これなら勝てる」
義元方は活気付き、玄広恵探方は動揺した。
「甲斐の武田が義元に味方したそうだ」
「福島が何度攻め込んでも勝てなかった武田が、義元に援軍をよこしてきたそうだ」
「どうやら北条も義元についたようだ」
義元方の勇将・岡部親綱(おかべちかつな)が方上城を奪い返すと、玄広恵探方は総崩れとなった。
玄広恵探は本城・花倉城も支えきれずに城を脱出、山を越えて瀬戸谷へ逃れたが、
「もはやこれまで」
と、あきらめて普門寺で自殺した。
義元は勝った。
戦う前に敵に戦意を喪失させることにより、損害を極力押さえることができた。
義元は還俗して駿府館に入り、今川家の家督を相続、駿河・遠江二か国の守護職に就任した。
義元は太原崇孚に礼を言った。
「師のおかげだ。これからも助言を頼む」
太原崇孚は駿府に移り、氏輝の菩提を弔うために臨済寺(静岡市)を建立、その住職になった。
以後彼は、義元の軍師として、その腕を存分に発揮することになる。